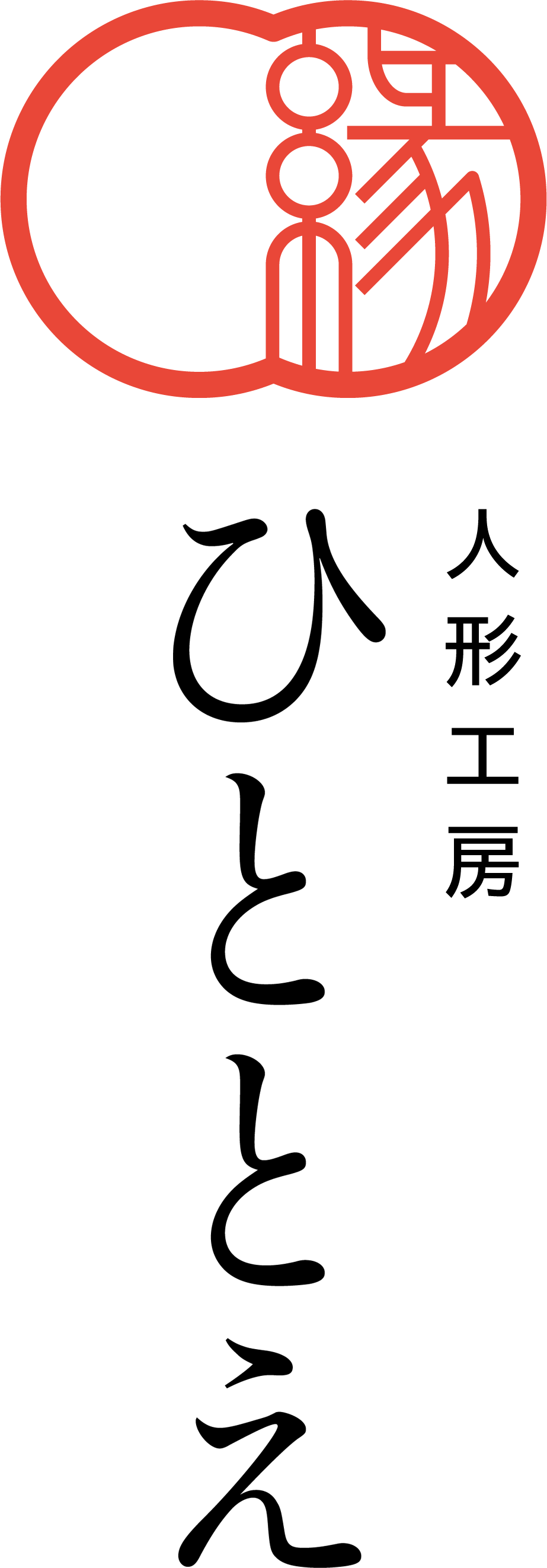〇「雛人形を早く片付けないと婚期が遅れる」は迷信
雛人形をしまう日について、昔から「早く片付けないとお嫁に行き遅れる」と言われます。これを信じて、雛まつりが済むと翌日には慌てて片付けるご家庭があるかもしれません。しかし、これは全くの迷信。「時期が過ぎたのに、いつまでもだらだらと飾らないようにしましょう」という戒めの言葉であって、婚期が遅れる理由に直結する訳ではないのです。
強いて言えば、「伝統行事であるお節句のお祝いをきちんとして、終わったら片付けを先延ばしせずてきぱきとしまう娘さんであれば、きっとよいお嫁さんになれますよ」という教育的な含みがあったのでしょう。娘を嫁がせるのは親の役目と考えられていたほんのひと昔前まで、娘を嫁がせることを「娘を片付ける」と表現しました。いまでも年配者が「うちの娘もやっと片付いたから」などと言ったりするのを聞いたことがありませんか。お雛さまが「片付く」ことと娘が「片付く」ことを重ねて、そんな俗説が生まれたのかもしれません。
ほかにも、「啓蟄(けいちつ)に片付けるのがよい」という説もあります。「啓蟄」は「立春」「雨水(うすい)」に続く二十四節気の3番目。「冬ごもりしていた虫が土の中から這い出てくる」いう意味で、3月6日頃にあたります。地域によっては、旧暦の雛まつりまで飾るところもあるそうです。
いずれにせよ、雛人形を片付ける時期と娘さんの婚期に相関関係はありません。じつはそれよりもずっと大切で、ぜひ守っていただきたい片付けのタイミングがありますので、つぎにご紹介していきましょう。
〇しまうタイミングはお日柄よりもお天気が優先
娘の婚期が遅れることを心配して、雛まつりが終わるとすぐに雛人形を片付けるご家庭もあれば、「お日柄のよい日に雛人形をしまいたい」と大安を選んで片付けをするご家庭もあるようです。確かに、片付けた日がたまたま大安であれば、何かいいことがありそうな気持ちになりますが、大安だから片付けると逆に考えるのは、失敗のもと。お日柄よりも優先してほしいのは、お天気なんです。
お雛さまは湿気が苦手。雛人形を片付けるときは、まず外気にあてて湿気を飛ばしてから、ホコリをよく払ってしまってほしいのです。そのためには、雨が降っている日や、雨の前後の湿度が高い日は不向きです。カラッと晴れて乾燥した日を選び、窓を開け放ち部屋に風を通して、雛人形を日陰干しにしてから片付けましょう。
湿気を十分に飛ばしたら、毛ばたきでホコリをよく払い、収納します。毛ばたきがないときは、やわらかい筆でもよいでしょう。片付けるときは、もともと収納されていた箱に、元通りに戻すのが原則です。しかし、飾り付けから1カ月も経過してしまうと、覚えたつもりの収納方法も意外と忘れてしまうものです。心配な方は、飾り付けのときに何が入っていた箱なのかをメモしておいたり、どのように収納されていたのかを写真に撮っておいたりすると便利です。
〇収納するときも湿気対策を万全に
収納前に風を通して湿気を飛ばした雛人形も、収納の仕方で台無しになってしまうことがあります。雛人形を片付けるときはもちろん、収納している間も湿気対策を講じる必要があります。
雛人形を収納するときには、紙でくるんで桐箱や紙製の箱にしまいます。防虫対策としてジップ付きのビニール袋や食品の保存などに使うプラスチック容器を使うアイデアが紹介されたりもしますが、湿気対策としてはNGです。ビニール袋やプラスチック容器に雛人形やお道具を収納してしまうと、中に湿気がこもってしまい、シミや黄ばみの原因になってしまいます。その点、吸湿性のある紙でくるんだり、調湿性の高い桐箱に収納したりすれば、雛人形に負荷がかかりません。
身代わりとなって厄を引き受けてくれる大切なお雛さま。正しい収納方法で、いつまでも美しく鑑賞したいものですね。
〇一年を通して雛人形を楽しむという考え方も
雛人形を片付けるタイミングについて、ここまでは慣例に基づいてお話してきましたが、現代では180度考え方を変えて「一年を通してお雛さまを楽しむ」というケースも増えています。コンパクトな木目込雛人形やケース飾り、インテリア性の高い立雛を、日本の伝統工芸品として季節を問わず飾っているおうちもあります。美しい雛道具をドールハウスのように飾るのも、なかなか素敵です。
かつて桃の節句に行われた厄除け行事から生まれたお雛さまは、やがて幼い子どもたちの厄を引き受ける民間信仰となり、江戸時代には幕府が定めた「五節句」の一つに数えられるようになりました。その起源を探ると、お雛さまの効力が子どもに限ったものではないことがわかります。自分の穢れや災いを払ってくれるようにと祈るのは、大人になっても変わりません。実際、初節句だけでなく、大人になってから自分のためのお雛さまを購入したいと工房を訪れるお客様も大勢いらっしゃいます。
心のよりどころが必要とされるストレスフルな現代、人知れず頑張りつづける自分を見守ってくれる厄除けの雛人形として、すぐそばに一年中飾っておくというのも、新しいお雛さまの楽しみ方になるかもしれませんね。